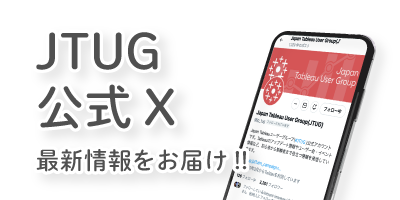みなさま、こんにちは。JTUGスポンサーチームのKevinです。
今回は、3年連続でJTUGのプラチナスポンサーとして支援いただいている、ちゅらデータ株式会社様へのインタビュー記事をお届けします。

オープニング
Kevin: 今回は、JTUGプラチナスポンサー、ちゅらデータ株式会社から、LowSE01さんとロンさんにインタビューする機会をいただきました。今日は、BI × AIをテーマにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします!
LowSE01: よろしくお願いします。ちゅらデータでデータエンジニアとして働いている、LowSE01と申します。Tableauとの関わりとしては、DATA Saberの4期卒業生で、JTUGサポーターズとしても活動しています。
Kevin: 4期生!DATA Saberの中でもかなりの古株ですね。よろしくお願いします。では、続けてロンさん、お願いします。
ロン: 私は昨年の夏に入社し、BIエンジニアとしてTableauなどのダッシュボードやデータソースの開発を担当しています。社内のBIギルド運営にも関わっていて、JTUGではデータレバレッジチームにも参加しています。データの準備や提供に関心があって、もっと深く関わりたいと思い活動しています。
ちゅらデータの紹介
Kevin: では簡単に、会社の紹介をお願いできますか?
ロン: ちゅらデータは「最高に面白い仕事を沖縄に創りたい」という想いのもと、社長の真嘉比が2017年8月に創業した会社です。事業は順調に拡大しており、社員数はついに100名を突破しました。社員の約9割はエンジニア職が占めており、主な事業はデータ分析やAI実装に向けたデータ基盤構築、AI技術コンサルティングなどです。社内にはギルドと呼ばれる技術的専門性によって分けられたグループあり、スキルアップや課題共有の場として機能しています。
Kevin: ギルドのような横断的な仕組みがあるのは素晴らしいですね。学び合える環境が整っているのは大きな強みになっているんですね。
BI×AIの最新事情とそれに感じること
Kevin: では本題に入ります。今注目のBI×AIについて、どんなふうに感じていますか?
ロン:生成AIの普及により、BIのセルフサービス化が本格的に進むと考えています。先日アメリカでTableau Conferenceの開催がありました。そこでTableau社は本当の「セルフサービスBI」を実現するというビジョンを発表しましたね。AIを介して、ユーザーが自然言語で分析を依頼すれば、可視化まで自動で出力してくれるような世界が見えてきました。エンジニアが作り込むのではなく、ユーザーが自らインサイトを得る環境へとシフトしていると思います。
Kevin: 確かに、セルフサービスBIがより本質的に近づいてきた印象を受けますね。
LowSE01: 一方で、現状ではまだまだ「人がおこなう操作の代替」の域を抜け出せていないのかなと感じています。たとえば「商品別の売上を月ごとのグラフにして」と言えば、AIがすぐにやってはくれますが、BI操作のエキスパートであるユーザーからしたら、それだけでは大きなアドバンテージにはならないかな、と感じています。
AIが全てのディメンションを網羅的に見て、有意なパターンを抽出してくれるようなレベルになってくると、ぐっと価値が増しますね。人間の経験や勘に頼る分析にはどうしてもバイアスを拭いきれない、かといってすべての組み合わせを手作業で網羅的に観測していくのは現実的ではないので、まずはそのあたりをAIがカバーできるようになってくるといいですね。
Kevin: なるほど。グラフを描くだけなら昔からできましたが、仮説に頼らず発見を導けるところがAIの力というわけですね。
LowSE01: そうですね。一方で、BIエンジニアとしての私たちの役割も変わっていくんだろうなと感じています。AIが示すインサイトを鵜呑みにせず、より良い意思決定のために判断材料を精査し、問を深めていく部分に関しては、まだまだ人間が介在し続けていく必要があると思っています。
Kevin: アクションを示すことがゴールではなく、それを評価・解釈する力が重要になってくると。
LowSE01: そうですね。そしてそれを支える「ビジネス理解力」と「データ理解力」が、この先より重要になってくると思います。どういう文脈でその数字が出てきたか、より正しい示唆を得るためにはどういったデータを与えていけばよいか、という部分を理解し、エコシステムとして整えていく必要があると思っています。
Kevin: エコシステム、大事なキーワードですね。Tableau Nextのような進化も、それを支える仕組みがあってこそ真価を発揮すると思います。
LowSE01: BIエンジニアとしては、この先もっと前後のプロセスまで踏み込んでいくことで、AI時代のBIの価値を高めていくための活動が大事になっていく。EDA(探索的データ分析)のような業務はAIに一気に代替される可能性がありますが、その先でBIエンジニアが発揮できる価値はまだまだあると考えています。
ロン: 従来のダッシュボード開発は減ってくる一方で、データの準備やカタログ整備、モデリングといった前処理の部分と、ユーザーのデータリテラシー研修はニーズが大きく伸びると私も考えています。そこに可能性を感じて、BIエンジニアとして活動の幅を広げていきたいと思っています。
BIはバックミラーからヘッドライトへ
Kevin: では、そんな中で、ちゅらデータとしてはどんな取り組みをされているのでしょうか?
LowSE01:成り立ちがAIコンサルティング事業なので、各方面においてAI活用を通じての課題解決を目指す、というところは当然としてありますね。とくにBIとの関連ついて言えば、TableauにおけるAgentforceのような「アクションまで提案してくれるBI」については、社長の真嘉比もずっと以前から構想していたアイデアの一つだったと聞いています。
Kevin: インサイトだけではなく、次に何をするべきかまで示すBIが求められているというわけですね。
LowSE01: 弊社のデータサイエンティストから出ていたフレーズとして、「BIはバックミラーからヘッドライトへ」というものがありました。これまでのBIは、記録された過去を振り返っての分析にとどまっていましたが、今後の動きを予測してアクションの示唆を出すような、未来を照らす役割にシフトさせていきたい。そのためには、必要な正しいデータを入力する、AIが提案したインサイトを人間が吟味し、また新しい情報をフィードバックする——そんなサイクルが必要という。
Kevin:それこそ、未来予測のローデータ自体をAIが生成していくような世界観ですね。
LowSE01: まさにそうです。そうした世界を実現すべく、ちゅらデータはデータの活用支援を通じて、お客様と伴走していきたいと考えています。
クロージング
Kevin: 今日はありがとうございました。インタビュー前のお話では「まだ取り組みと言えるほどのものは…」とおっしゃっていましたが、お二人の発言からは、未来を見据えた強い問題意識とビジョンを感じました。
LowSE01: ありがとうございます。BIは大きな転換期にあり、お客様のニーズと期待も変わってきます。それにしっかり応えていくため、1エンジニアとしても組織としても邁進していきたいと思います。
Kevin: 今後の取り組みも、ぜひまた聞かせてください。本日はどうもありがとうございました。
(了)
(2024年度JTUGプラチナスポンサー特典)